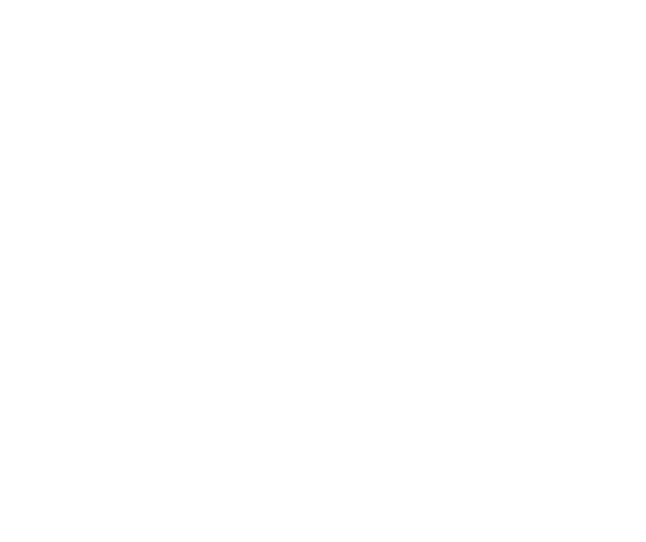
福島のFacebook
新着情報
- 2024/04/08(月) お知らせ 4月のイベント情報
- 2024/03/18(月) お知らせ 3月のイベント情報
- 2024/03/05(火) お知らせ ホームページリニューアル
食の真髄を知る旦那が贈る
自慢の料理でおもてなし
福島でお客様にご提供します料理は食材にこだわり厳選したものを使用しております。
釣りの腕、目利きの腕には自信があり、美味しい魚を、美味しい時期に召し上がって頂けます。
また、魚介類だけではなく肉にもこだわっており、福島で使用しているお肉は最高品質の《若狭牛》。
鮮やかな霜降り、きめの細かく、柔らかな肉質が特徴です。
食材にこだわった福島の料理をご堪能下さいませ。

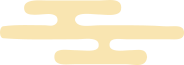



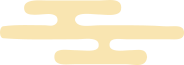
耳を澄ませば聞える潮騒。
心安らぐ空間へ
当館は海の目の前に佇む民宿です。
その為、客室の窓からは広大に広がる大海原。館内の何処にいても海が望め、潮騒が聞こえます。何もない福島だからからこその特権。
都会の喧騒から離れた片田舎で静かなひと時を過ごしてみてはいかがですか。

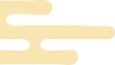
海と山の自然体験。
忘れる事のないご旅行に。
民宿福島は福井県大飯町に位置し、西は歴史の街《京都》、東は大自然が織りなす港町《敦賀市》、南は日本一の湖をもつ《滋賀》がございます。
自然で遊ぶも良し、歴史と触れ合うも良し、立地を活かした遊び方をご紹介いたします。












 0770-77-0095
0770-77-0095